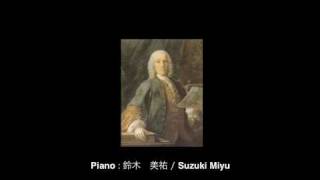スカルラッティ, ドメニコ : ソナタ ホ長調 K.162 L.21
Scarlatti, Domenico : Sonata E-Dur K.162 L.21
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:5分20秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:展開1 展開2 展開3
楽譜情報:3件解説 (1)
演奏のヒント : 大井 和郎
(801 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (801 文字)
このソナタの課題として、リズムからピッチから全てが全く同じに書かれている箇所をどのように弾くかと言う事が挙げられます。シークエンスであれば上行・下行、向かって行く場所の強弱等色々考えてクレシェンドをかけるなり、ディミヌエンドをかけるなりできるのですが、全てが全く同じに書かれている箇所は、平坦に、単なるリピートとして強弱すら同じに弾けば良いものかどうか、その辺りを考えていかなければなりません。
そのような箇所を、同じように弾くことに対して筆者は否定をしているわけではなく、それは1つの演奏法だと思っています。「心地よいしつこさ」 とでも比喩したら良いでしょうか。一方で、強弱、音質等を変化させることで、方向性が定められたり、音楽そのものの意表を突いたり、色々なことが可能になります。
例えば84〜85小節間 と、87〜88小節間は全く同じです。それが過ぎた後、すぐまた、88小節目3〜4拍間と、89小節目1〜2拍間、同小節3〜4拍間は、全て同じです。また、90〜91小節目2拍目まで、と、91小節目3拍目から、92小節目4拍目までも全く同じです。
これらの箇所の処理方法として、強弱を変え、1回目フォルテ、2回目ピアノ、というのは典型的な手法ですが、1回目より2回目を大きくするので、も、ユニットユニットで考えず、その箇所全体にクレシェンドやディミニュエンドをかける、という可能性も十分に考えられます。あるいは、それらの素材の一部分だけ変化を付ける事も可能です。例えば、90〜92小節間で、90小節目から92小節目の2拍目まで同じ音量で演奏し、92小節目の3〜4拍で急激なクレシェンドをかけることも可能です。色々考えてみて下さい。
編曲・関連曲(1)
ピティナ&提携チャンネル動画(3件)
楽譜
楽譜一覧 (3)

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)音楽之友社