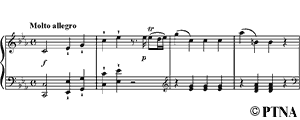モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第14番 第1楽章 K.457
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.14 Mov.1 Allegro
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(652 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (652 文字)
第1楽章 ハ短調 4分の4拍子 ソナタ形式
3オクターヴのユニゾンで主和音の分散和音を奏でる主要主題によって決然と開始される。半音階下行の内声進行をもつ経過句(第9小節~)を経て、平行長調の変ホ長調へと至り、旋回音型による装飾と、半音階的な変化音によって修飾された副次主題があらわれる(第23小節~)。続いて、上声部と低声部に対話風にあらわれるもう1つの副次主題があらわれる。半音階を多く含むパッセージと主要主題の動機による経過句となる。前半部分は、本来、副次主題の調性で閉じられるが、このソナタでは、主調の属9和音という開かれたままの状態となっている。
開かれた状態とされた前半の締めくくりは、一方では反復記号による冒頭への、他方では後半部分への接続を果たしている。後半部分(第75小節~)は、まずハ長調による主要主題で開始され、ヘ短調で最初の副次主題(第79小節~)と主要主題(第83小節~)があらわれる。そして主要主題が8分3連音符をともない、ト短調、ハ短調と転調し、前半の締めくくりと同様、属9和音へと至り、属7和音上に停止する。長いフェルマータが置かれた99小節目では、当時の演奏慣習としてアインガングを挿入することも可能であろう。
主要主題の再現(第100小節~)の後、最初の副次主題の再現は省略され、主要主題の動機が多声的に展開する(第118小節~)。そして2つ目の副次主題を主調で再現する(第131小節~)。さらに、主要主題によるコーダが用意されており(第168小節~)、最弱奏で楽章を閉じる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(582 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (582 文字)
モーツアルトが扱うC-mollという調は、彼にとっては特別な調だったと想像出来ます。このソナタの後に続く、fantasyもそうなのですが、単に楽天的には留まらず、深刻で、独自な一面も見せる調として選ばれています。Es-durのコンチェルト、ジュノムの第2楽章も平行調のC-mollですが、似たようなムードですので、是非参考に聴いてみて下さい。
この第1楽章も、オペラの1シーンとして考え、オーケストラの部分と歌の部分を分けて考えて下さい。仮にですが、1〜2小節間のオクターブをオーケストラとたとえ、2小節目3拍目から始まるpの部分を歌と考えることもできます。実際に歌としては速すぎるパッセージもあるかも知れませんが、基本的には背景に歌を感じて弾いて下さい。
22〜43小節間は明らかに歌の部分です。23小節目の右手に書かれてある32分音符も歌の部分ですが、あまりこの部分が速すぎたり、機械的にならないように注意します。歌の部分として意識するとは、そのような配慮のことを指します。36〜43小節間は,もう1人の歌の人が登場し、かけあいの部分になります。女性と男性の掛け合いと考えても構いません。
ピティナ&提携チャンネル動画(4件)
楽譜
楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス