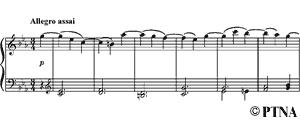モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第14番 第3楽章 K.457
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.14 Mov.3 Molto allegro
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(464 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (464 文字)
第3楽章 ハ短調 4分の3拍子
ロンド主題は、Allegro assai(agitato)という急速なテンポの中、アウフタクトとタイによって結ばれたシンコペーション・リズムによって、1拍ずれたヘミオラのような旋律を、拍節通に刻まれる和音が支える。
属7和音の上に停止し、総休止によって緊張感を持続させた後にドッペル・ドミナントへ進行する件(第24小節~)は、19世紀のロマン派和声(例えばワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』のような)を先取りしているかのような緊張感をもっている。
平行長調の変ホ長調によるクープレ主題にも、半音階パッセージが認められる。そしてロンド主題の回帰(第103小節~)の後、クープレ主題が主調であらわれる(第167小節~)。
第221小節からのロンド主題回帰には、a piacereの指示をもった属7・属9和音を積み重ねる部分が挿入されている。こうした和声的緊張感の高まりは、モーツァルトの短調作品における特徴の1つといえるだろう。そしてコーダでは、音域を広範に拡大し、楽器のほぼ全音域を使用して楽曲を閉じる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(745 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (745 文字)
いくらAllegro assaiとは言え、Prestoのように速く弾くと、16分音符がクリアーに聞こえなくなる恐れがあると同時に、左手が必要以上に大きくなってしまいますので、テンポは、例えばですが、ご自分で3拍子を指揮してみて、速すぎないテンポが望ましく感じます。
ここからは筆者の個人的な趣向も入ってしまうのですが、例えば18小節目3拍目に出てくる右手の16分音符は、楽器にたとえたらどの楽器なのでしょうか?テンポがあまりにも速すぎると、この16分音符4つはほぼ同時に弾かれることになり、発音がクリアーにならない事が懸念されますし、もう1つは例えば、17〜20小節間の左手の問題もあります。これはフォルテマーキングがわざわざ下方に書いてありますので、大きく弾かなければならない呪縛となってしまうのですが、この4小節間の左手を、もの凄く速いテンポで、しかもフォルテで弾いたらどのような事になるでしょうか?かなりガチャガチャした音楽になってしまいます。テンポはさておいたとしても、ここのフォルテはあまり正直に守らない方が無難です。
加えて、アーティキュレーションの問題もあります。1〜8小節間の右手のスラーをご覧下さい。アーフタクトから始まり、スラーは2小節目2拍目までで1度切れます。同様に、4小節目2拍目、6小節目2拍目、と言った具合ですが、これはヴァイオリンのボーイングと考えます。1度フレーズを終わらせてから新たに弓を上に上げて2つ目を弾き始めると考えますので、これらのスラーは、切れ目をしっかりと守って下さい。
ピティナ&提携チャンネル動画(4件)
楽譜
楽譜一覧 (8)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス