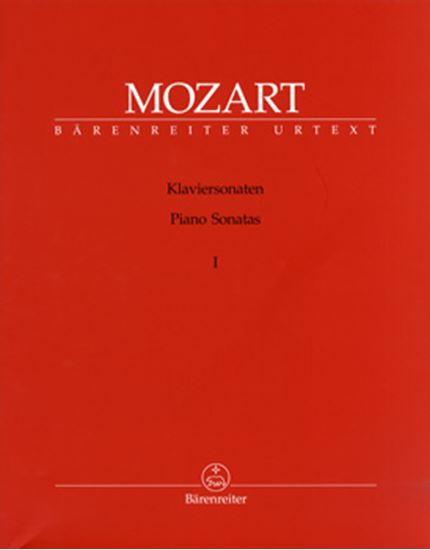モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第4番 第3楽章 K.282 K6.189g
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.4 Mov.3 Allegro
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:2分00秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:応用7 発展1 発展2 発展3 発展4
楽譜情報:9件解説 (1)
演奏のヒント : 大井 和郎
(741 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (741 文字)
第1楽章から、第2楽章を経て、曲はプログラマティックに進行し、この華やかで活気に満ちた第3楽章を迎えます。
特にこれと行った注意点はなく、2拍子を感じ、活気に満ちて演奏して良いと思います。
ところで譜面上、気になる点が1つだけあります。それは、20〜21小節間に見られる右手の書法で、右手は和音が4分音符でかかれており、1番上の音だけが2分音符で書かれています。しかしながら、4分音符であれば、もう1つ4分音符が入るか、あるいは4分休符が入らないと2拍になりません。
これは、作曲家の意図がよくわかりませんが、手のサイズの小さな人で、和音が押さえられない人の為に、下の音は離しても良いけど、上の音だけは繋ぐように という意味かも知れません。しかしここは、手のサイズが、4つの音で構成されている和音をつかめるサイズであれば、1番上の2分音符のみではなく、4つとも押さえて2分音符分伸ばして良いと思います。
さて、この楽章も基本的にはフォルテとピアノしか、強弱記号が書かれておらず、ピアノとフォルテが交互に現れます。前の2つの楽章でも述べましたが、とにかく、強弱記号を鵜呑みにせず、状況状況に応じて臨機応変に変えてください。例えば今お話をした、20〜21小節間ですが、あまりにも左手がフォルテで弾いてしまうと、耳障りの原因となります。最終的にフォルテになっていれば良いのであって、全部の音をフォルテで弾けという事ではありません。この楽章の場合、16分音符が1小節内に8つ入り込んでくると、それだけでも音量は出てきます。
ピティナ&提携チャンネル動画(7件)
楽譜
楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)