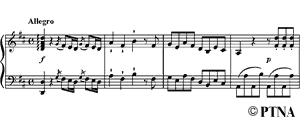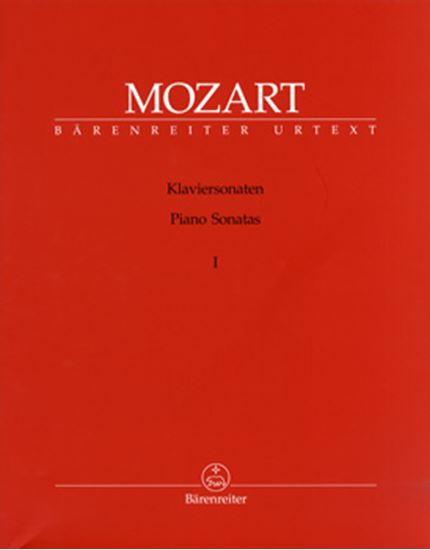モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第6番「デュルニツ」 第1楽章 K.284 K6.205b
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.6 'Dürnitz' Mov.1 Allegro
作品概要
解説 (2)
解説 : 稲田 小絵子
(105 文字)
更新日:2021年2月26日
[開く]
解説 : 稲田 小絵子 (105 文字)
アレグロ、ニ長調、4/4拍子。ソナタ形式。マンハイム楽派の影響とされるのは、アルペジオによる華やかな開始、強弱をはっきり対照させること、下行2度の「ため息」音型の使用などである。交響的な幅広い響きをもった楽章。
演奏のヒント : 大井 和郎
(854 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (854 文字)
楽しく、おしゃれな第1楽章です。まさにオペラのシーンであり、「オーケストラと歌」という位置づけで間違いありません。特に、どの部分が歌で、どの部分がオーケストラであるかと言う事は、厳密に分類する必要も無いと思います。例えば30〜32小節間、オーケストラの部分とも取れますし、ト音記号に書かれているメロディーを抜粋すると、30小節目は、H Ais H Ais H という5つの音の部分が歌の部分とも想定できますので、その辺りは自由です。
さてこの第1楽章は特徴的なリズムがあり、12小節目1拍目、右手に登場する、付点8分音符+2つの32分音符です。このリズムがあっちこっちに書かれています。単なる、8分音符+2つの16分音符よりも、より一層ウイットに富んだ表現ですね。しかしこれが大きな問題となる部分があります。
それは40小節目に登場する同じリズムで、1拍目、右手に書かれています。しかしながらこれが、ある程度のテンポで進んだとき、ほぼ物理的に演奏ができないユニットになっています。32分音符の部分がどうしても弾けません。そしてここからは皆様の判断に委ねます。方法は2つあります。1つは、
全ての音をきちんと弾くため、このような40小節目であるとか、43小節目のようなユニットは、リズムを崩し、8分音符+2つの16分音符のように弾くというやり方です。実際にプロのピアニストのレコーディングでこの方法を取っている方もいます。
もう1つは,32分音符の部分の内声を省くことです。40小節目であれば、1拍目、内声の D と H を抜かしてしまいます。そうしてでもリズムを正確に保つ方法です。皆さんはどう思われますか?筆者であれば、リズムを保ち、音を省略する方法を取ります。そうしてでもリズムが大切と感じるからですが、それはその奏者の判断となります。
ピティナ&提携チャンネル動画(0件)
楽譜
楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)