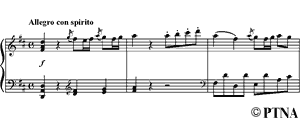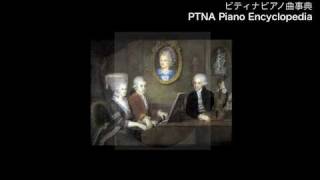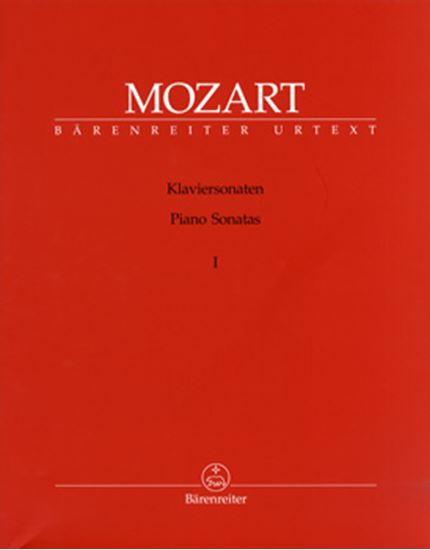モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第8(9)番 第1楽章 K.311 K6.284c
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.8 Mov.1 Allegro con spirito
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(295 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (295 文字)
第1楽章 二長調 4分の4拍子 ソナタ形式
K.309と同様、オーケストラのトゥッティのような力強い開始と、それに呼応して弱奏の軽快なメロディーが流れだす。属調の副次主題(第17小節~)はレガートとスタッカーによる順次下行音型の対比が特徴的である。
後半部分(第40小節~)は、前半部分を締めくくる2度下行音型の連鎖がゼクエンツ風に続き、ホ短調、ロ短調を経てト長調で副次主題の下行音型があらわれる。16分音符の連鎖による移行パッセージ(第66小節~)の後、まず副次主題が主調で再現される(第79小節~)。主要主題はようやく第99小節で回帰し、前半と同様に2度下行音型によって静かに楽章を閉じる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(844 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (844 文字)
劇的な要素が強い第1楽章です。とても楽しく、楽天的な傾向で、深刻な事はありません。故に決して重たくならないようにします。軽やかに弾くにあたりネックが1つあります。それは、2つの音が、スラーで繋がれているユニットです。3小節目1〜2拍間の右手のように、AとFisがスラーで繋がれている場合、これは4分音符ですので、さほど問題が無いのですが、17〜19小節間の1拍目右手のように、8分音符で2つの音がスラーで繋がれているユニットは気をつけます。
基本的に、これら、スラーで繋がれている2つの音は、前の方の音に少しだけ軽いアクセントを付け(決して強すぎてはいけません)、後ろの方の音を、抜くように、短く切り、音量を落とし、消えていくように弾きます。故に、手は、後ろの音を弾いた瞬間に上に上がるようなモーションにします。
決して後ろの音が長くなったり、前の音より大きくなったりしないように、消えていくように、軽やかに弾きます。これが重要です。
この奏法を、38小節目の右手にも使います。続いて、展開部は55小節目まで、このユニットが右手にも左手にも登場しますので、同じように、後ろの音を短く切って下さい。
ところで、これらの、スラーがかかっている2つの音が、38小節目のように4つ連続して出てくるときは、4つ目が終わり、次の音が、向かって行く音になります。つまり38〜39小節間では、39小節目の1拍目の2分音符が向かって行く音になりますので、2つの音の後ろの方を弱く弾く秩序を守りつつ、39小節目1拍目に向かってクレシェンドをかけていき、39小節目に達したら、そこからディミヌエンドをかけます。
同じように、展開部も、2小節単位でフレーズが来ますので、向かうポイントは、4つの、スラーがかけられているユニットの次の音になります。
ピティナ&提携チャンネル動画(3件)
楽譜
楽譜一覧 (10)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス