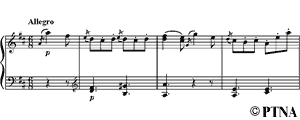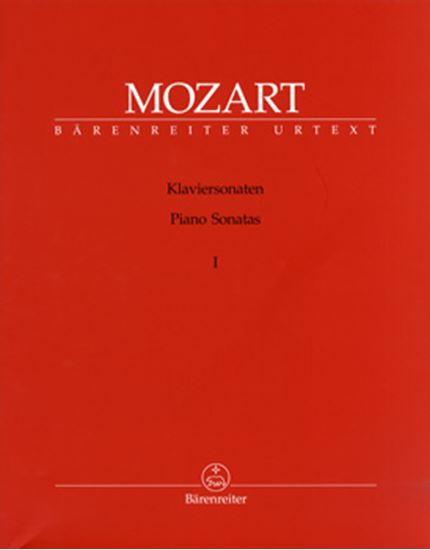モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第8(9)番 第3楽章 K.311 K6.284c
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.8 Mov.3 Rondeau: Allegro
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(214 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (214 文字)
第3楽章 二長調 8分の6拍子 ロンド
このソナタの終楽章もロンドであり、K.309とまったく構成を同じくしている。
前打音の装飾をともなう軽快な主題によるロンド。音階の連続や長いクープレ主題など、即興的なパッセージを多く含む点もK.309と極めて類似している。
3度目のロンド主題回帰の直前には、通常は記譜されない、即興で演奏されるアインガングが、実際に書かれている点は、演奏慣習等を含めたさまざまな視点からも、興味深いものである。
演奏のヒント : 大井 和郎
(754 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (754 文字)
優雅で華やかな第3楽章です。スタッカートが多く書かれていますが、全体が重たくならないようにという意味と理解します。スタッカートが書かれていない箇所でもスタッカートにすることで、軽快感が出ます。例えば、4小節目,5小節目の2拍目の左手の8分音符、2小節目1拍目裏拍の右手3度、16〜18小節間の8分音符、27小節目各拍の裏拍に書いてある8分音符、29小節目左手8分音符、33〜37の左手8分音符等をスタッカートで弾いて構いません。むしろ推奨します。
1つ考えたいのは、同じ音とリズムが2回(以上)続くときの変化のしかたです。例えば、21小節目の右手と、23小節目の右手は全く同じですが、同じように弾いた方が良いでしょうか?それとも違いを付けた方が良いでしょうか?
全く同じリズムと音が2回(以上)続くときの解釈の仕方としては、同じ台詞を2回歌っていると考え、それは、何度もお願いをしたり、同じ台詞を何度も言うことで強調したりという考え方もできます。
筆者であれば、おそらく、2つの同じ小節に対しては違いを付けると思います。例えば、21小節目の装飾音(ターン)は普通に弾き、23小節目の装飾音は少しゆっくり目に弾くことで、落ち着きが出ます。
そうなると、4小節目2拍目から5小節目1拍目まで、と、5小節目2拍目から、6小節目1拍目も全く同じ音とリズムです。これらの違いも付けるべきでしょうか?また、33〜34小節間と35〜36小節間の違いは必要でしょうか?その他、この第3楽章には多くの、同じ音とリズム があります。色々試し、考えてみましょう。
ピティナ&提携チャンネル動画(2件)
楽譜
楽譜一覧 (10)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)