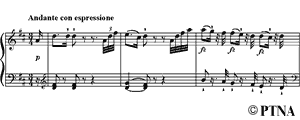ハイドン : ソナタ 第56番 第1楽章 Hob.XVI:42 op.37-3
Haydn, Franz Joseph : Sonate für Klavier Nr.56 Mov.1 Andante con espressione
作品概要
解説 (2)
解説 : 大井 和郎
(874 文字)
更新日:2025年4月3日
[開く]
解説 : 大井 和郎 (874 文字)
この第1楽章はハイドンのピアノ曲の中でも大変難しい曲に分類されます。それは技術的な問題では無く、考え方の問題です。Andanteまでは良いのですが、次の、con espressione が問題なのです。判りやすい言い方で言う
と、機械的に処理されやすい曲とご理解ください。そしてどのような弾き方
をすれば機械的にならずに、con espressione になるのか考えていきましょ
う。
書かれてある32分音符や3連符などを正確に演奏することはとても大切な事
ですが、それが一度身についたら、それから先はメトロノームの様に、ある
いは、打ち込んだシンセサイザーのように、正確に弾く必要はありません。
むしろ崩して頂きたい曲です。
1つのヒントとしては、オペラのアリアと考えても良く、メロディーラインを歌の線と考えます。その時、あまりにも32分音符や32分音符の3連符が機械的に演奏されたら、歌自体が奇異に感じられると思います。また、この曲を弦楽4重奏と考え、多くのスラーを、ヴァイオリンのボーイングと考えた時も、機械的な演奏を避けると思います。3小節目の様な所を、あまりにも、躍動的に、スタッカートで弾いたらどうなるでしょうか?そしてこの3小節目のフレーズは、4小節目1拍目のメロディーラインFisに到達させる方向性が必要ではないでしょうか?そうすると、強弱も変わってきますし、あまりにも、スラーをかけられている2つ目の音を、元気に、短く切ってしまうことで、本当に機械的な演奏になってしまいます。
3小節目の1拍目表拍のAは、稽留音です。そしてそれは次のGに解決されるのですから、Gにはアクセントを付けず、ヴァイオリンの弓がゆっくり離れるように、柔らかく弾かれるべきです。
5小節目の1拍目メロディーラインの、DEDCisDECis というユニットも
実に機械的になりがちです。Eに方向性を定め、最後のCisは消えるように弾
きます。その他、多くの細かい音符のパッセージも全て、音楽的に、メロ
ディックに弾いて下さい。それが、con espressione という意味です。
解説 : 齊藤 紀子
(317 文字)
更新日:2021年2月26日
[開く]
解説 : 齊藤 紀子 (317 文字)
第1楽章のニ長調は、アンダンテ・コン・エスプレッシオーネの4分の3拍子。この楽章は、ソナタ形式ではなくロンド形式で書かれている。そのロンド主題は、上行音形に基づいており、それに伴う左手の音域も高音部記号で書かれていることが多い。最初の副次的主題は、左右の手による会話を思わせるものとなっている。その後、回帰するロンド主題は、冒頭の1オクターヴ下で開始し、冒頭と同じところまで上昇する。従って、上昇する性格を更にきわめていると言える。その後、挿入される副次的主題は、先の副次的主題の左右の登場順番を入れ替えたものとなっている。この楽章の最後に回帰するロンド主題(第94小節~)は、細かく装飾的な音に富んだものとしてリズム変奏されている。
ピティナ&提携チャンネル動画(3件)
楽譜
楽譜一覧 (7)

ヘンレー

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレ社(ヤマハ)