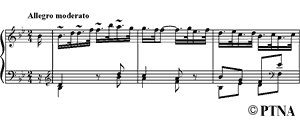ハイドン : ソナタ 第20番 第1楽章 Hob.XVI:18 op.53-3
Haydn, Franz Joseph : Sonate für Klavier Nr.20 Mov.1 Allegro moderato
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:5分30秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:発展1 発展2 発展3
楽譜情報:6件解説 (1)
演奏のヒント : 大井 和郎
(727 文字)
更新日:2025年1月26日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (727 文字)
古典派時代の2拍子という拍子は、基本的にかなり速いテンポで進みますが、この第1楽章のように、moderatoの表記があったとしても、拍子的にはかなり遅くならざるを得ない書法で書かれています。即ち、あまりにも細かい音符と装飾音が書かれてあるため、これらを余裕を持って弾くためには、遅いテンポで無ければ難しく、下手に速くしてしまって、装飾音等を弾く余裕が無くならないようにします。即ち、2拍子を感じながら弾く必要が必ずしも必要では無いような気もします。
それはさておき、この第1楽章で大事なことはタイミングの問題になります。先ほど2拍子は感じなくても良いと申し上げましたが、しかしながら、何拍子であろうとも、拍はコンスタントに進まなければならなく、何らかの事情によって、余計な時間を食ってしまっては、聴き手が拍を失う結果になります。
例えば9小節目、ターンの最初の音が、1拍目の表拍にしてしまうと、それが終わるまで、左手はスタートすることが出来ず、結局ターンが原因で、余計な時間が出来てしまうことになります。我々は演奏の時に常に忘れてはならない事は、聴き手は拍を感じて聴いているかもしれないということで、聴き手に対して拍を裏切らないように弾くことが大事です。
ではどうすればいいかという話になりますが、この9小節目で例を取ると、ターンの最初の3つの音はEs D Cis ですが、この3つを前の小節の最後に弾いてしまいます。8小節目で、休符があろうとも、正確に数え、ターンの4つ目の音が、9小節目の1拍目表拍にピッタリ当てはまるように演奏して下さい。以下、似たような場所や、長い音符のある場所、長い休符のある場所では、特に気をつけて、カウントを正確に数えてください。
ピティナ&提携チャンネル動画(0件)
楽譜
楽譜一覧 (6)

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレー

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス