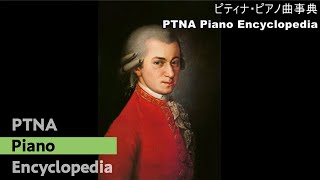モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第1楽章 KV 547a Anh.135
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate I. Allegro KV 547a Anh.135
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:6分20秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:応用7 発展1 発展2 発展3
楽譜情報:1件解説 (1)
演奏のヒント : 大井 和郎
(923 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (923 文字)
これから述べる事は、筆者の見解であり、「正・誤」の問題では無い事をご承知おき下さい。このソナタは器楽を意識していて、オーケストラをイメージできる部分や、弦楽4重奏をイメージする部分も出てきます。故に、器楽的に考えてお話しを進めます。
冒頭1〜3小節間、左手は、4分音符が1拍目と2拍目にそれぞれ2つ書いてあり、筆者の楽譜には2拍目でペダルを上げる、アステリスクが書いてあります。実際その通りに従ったレコーディングもあります。筆者には、1拍目にtuttiさながらの大きな編成の後に、2拍目で音数は半分に減り、しかもバスも失ってしまうというペダリングに違和感を感じます。仮に筆者であれば、1〜2拍間、ペダルを踏み続け、3拍目でペダルを上げると思います。ペダルを2拍目で変えるヴァージョンと、2拍間踏み続けるヴァージョンの両方を試してみてください。
モーツアルトの楽譜に書かれてある強弱記号は、時に鵜呑みにしないほうが良い場合もあります。例えば4小節目のように、2拍目にpマーキングが来ることは理に適っています。つまり、4小節目の1拍目まで、tuttiのフォルテが続くことを意味し、2拍目から小編成のグループがpで演奏するからです。しかし、筆者の楽譜には、16小節目の1拍目にフォルテのマーキングが書かれてあります。レコーディングの中には、この強弱記号に忠実に従い、1拍目から突然フォルテで演奏する演奏があります。しかしながら、この1拍目のFは、前の小節である15小節目のフレーズの最後です。従って、16小節目から音量が上がると仮定しても、1拍目右手のFだけは、前の小節3拍目のGから下りてくると考えますので、GよりもFを弱く弾くようにします。
そして、そもそも、12小節目1拍目は9〜11小節間のtuttiのエンディングですのでこれはフォルテで弾き、2拍目から弦楽4重奏が始まると考えます。この弦楽4重奏のアンサンブルが終わるのが16小節目の1拍目という風に考えます。ご参考まで。
楽譜
楽譜一覧 (1)

(株)音楽之友社