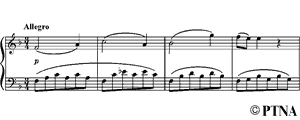モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第12番 第1楽章 K.332 K6.300k
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.12 Mov.1 Allegro
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:6分30秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:発展1 発展2 発展3 発展4 発展5 展開1 展開2 展開3
楽譜情報:9件解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(317 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (317 文字)
第1楽章 ヘ長調 4分の3拍子
主要主題は、分散和音の流麗な動機と、3度の重音による付点リズムと同音反復が特徴的な角笛風の動機からなる。分散和音と下降音階による移行部(第23小節~)は、二短調、ハ短調を経て、ハ長調(属調)の副次主題(第41小節~)があらわれる。充填リズムが特徴的な移行部(第56小節~)、コーダ(第86小節~)を経て前半を閉じる。
後半(第94小節~)は主要主題の素材を用いてハ長調(属調)で開始され、続いて副次主題移行部の素材があらわれる。ハ短調、ト短調、二短調と転調を繰り返してヘ長調のドミナントへ至り、主要主題の主調再現(133小節~)が始まる。移行部を経て副次主題を主調で再現(第177小節~)して楽章を閉じる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(730 文字)
更新日:2025年7月21日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (730 文字)
楽天的な傾向にある第1楽章ですが,考えなければならない課題もあります。まずはアーティキュレーションの話になります。多くの奏者は、4小節目右手の、FE E を弾くとき、ほぼ全ての版に書いてあるスラーに従い、FE レガートで繋ぎ、Eで1度音を切ってから、次のEを弾きます。これはこれで良いのですが、1〜3小節間はどうなのでしょうか?多くの奏者は1〜3小節間の右手をすべてレガートで繋いでしまいます。ペダルを踏んでも良い場所とも思いますが(バスがFであることと、非和声音が1〜3小節間には無いと言うことから)、ペダルを踏めば、尚更そこに書かれてあるアーティキュレーションを無視する結果にもなります。
即ち、1小節目はFからAにスラーがかけられており、Aで1度切ることが望ましく、2小節目はCからAにスラーがかけられており、Aで1度切ることが望ましく、3小節目はBからGまでスラーがかけられており、Gで1度切ることが望ましいのですが(ヴァイオリン等のボーイングと考えます)、多くの奏者はここに書かれているアーティキュレーションを無視します。
筆者の個人的な意見とはなりますが、ここに書かれているアーティキュレーションを守って弾いて欲しいです。
そうなると、例えば185小節目右手のオクターブにかけられているスラーも、Aで1度切ることが望ましいのですが、ここはペダルを使わないとスムーズに弾けません。そこでペダルを1拍ずつ踏み変えます。そして、1小節間に3つのユニットが出来るように演奏してください。
楽譜
楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス