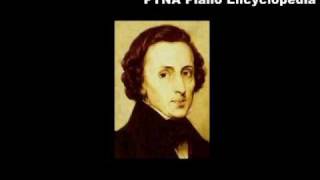作品概要
解説 (2)
執筆者 : 朝山 奈津子
(1731 文字)
更新日:2008年7月1日
[開く]
執筆者 : 朝山 奈津子 (1731 文字)
「舟歌(バルカロール)」はヴェネツィアのゴンドラ漕ぎの歌に由来するといわれている。8分の6拍子で軽快な動きを伴うが、どこか感傷やもの悲しさを含んでいるのが多くの「舟歌」の共通点である。しかし、これをジャンルとしてその伝統を辿ることはほとんど不可能である。おそらく流行の始まりは19世紀のオペラにこの種の歌が好んで用いられたことにある。ピアノのための作品としては、メンデルスゾーンが『無言歌集』所収のものを含めて3曲を残したほか、ショパンのものが最大規模かつ最高の佳作である。また、フォーレは13曲を書いていることから、ジャンルとして「舟歌」に取り組んだものと考えられる。しかしそれ以降は再び散発的な作品に留まっている。「舟歌」はジャンルと言うよりは、19世紀中盤から20世紀にかけて長く流行した性格小品のひとつというべきだろう。
ショパン《舟歌》は、いっけんすると、ロンド風に冒頭主題が繰り返し現われ、合間にさまざまなエピソードが挿入されているように聞こえる。そのため、ヴェネツィアの街を小舟で巡る――たとえば繰り返し回帰する主題は、「大水路」の風景に相当する、といった――風景描写的な解釈も可能であろう。しかし《舟歌》は実は、ショパンの中でも整った形式を持ち、優れて精緻な主題労作が施されている。
各セクションは、次のように区分できる。
小節番号 | セクション | 調 |
1-3 | 序奏 | Fis: 主調 |
|
|
|
4-16 | 第1主題 | Fis: 主調 |
17-23 | 間句 |
|
24-34 | 第1主題(確保) |
|
|
|
|
35-39 | 間句 | Fis-A 主調から同主短調のiii度長調へ |
|
|
|
40-50 | 第2主題前半 | A:/fis: |
51-61 | 第2主題前半(確保) |
|
62-71 | 第2主題後半 | A: |
|
|
|
72-77 | 間句 | Cis: 属調 |
78-83 | 挿入句 |
|
|
|
|
84-92 | 第1主題(再現) | Fis: 主調 |
93-102 | 第2主題後半(再現) |
|
103-110 | 第2主題前半(再現) |
|
111-116 | 終結句 |
|
つまり、複数主題の提示、ブリランテなパッセージワークによる中間部、主題の再現という、ショパンがもっとも多用する三部形式の一種である。しかしこの作品では、中間部がひじょうに縮小されている上、美しい旋律に依存するような単純な反復ではなく、巧みな主題が配置がなされている。
第1主題と第2主題前半は、絶え間ない8分の6拍子のオスティナート・リズムに攪乱されるが、音楽内容はきわめて対照的である。調は同主短調に移る。また、第1主題が下行形旋律であるのに対し、第2主題前半は上行形である。第2主題後半は調以外には前半とそれほど明確な繋がりはない。この主題が持つ華やかさは、ここではまだ音量によって抑えこまれている。
中間部では、わずか5小節ながら、8分の6拍子の刻みが一瞬やんで、拍節リズムに収まらない自由な時間の流れになる。しかしこの部分は単に、異なる時間の流れを意識させるに留まり、ショパンの中間部特有の旋律美を聴かせるには至らない。
再現部は、第1主題の変奏から始まり、一瞬の休符をクライマックスとして完全終止し、主調のまま第2主題後半へ突入する。続く第2主題前半の再現は、後楽節のみを用い、ときおり同主短調の響きを覗かせつつ、壮大な物語を終わりへと導いていく。ここはすでにコーダの領域であり、第2主題後半の壮麗な回音型動機で最高潮を形成し、前半後楽節の多層的で下行形の動機によってそれを収束させている。こうした動機の使い方は実に見事という他はない。
このようにみると、ショパンの《舟歌》はフォーレのそれとは異なり、抒情的な音楽というよりはむしろ、《スケルツォ》や《バラード》と同種の疑似ソナタ形式による物語的な音楽である。しかしそれが硬直した図式に陥らないのは「つなぎ」の巧さにある。序奏の3小節や第35-39小節の間句、各セクションの始まりを告げる重音トリルなどは、全体の動機労作とほとんど関係ないからこそ、わずか数小節で聴き手の耳を捉え、音楽の雰囲気をがらりと変化させてしまう。全体は自然に流れ、あたかも羅列的に、あるいは抒情的に聞こえるのである。この作品こそ、物語性と抒情性とを見事に融合させたショパン晩年期の最高傑作のひとつと呼ぶにふさわしい曲である。
演奏のヒント : 大井 和郎
(2625 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (2625 文字)
演奏のヒントと言うよりかは練習のヒントと言った方が良いかもしれません。この曲を練習する際に必要な事は「忍耐」です。練習してもしても上達の仕方が他の曲と比べ極端に遅いと思われる読者の方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。筆者にも該当します。この曲はとても大変で、効率の良い練習方法は勿論のこと、何度も同じ事を繰り返して慣れていく忍耐も必要になります。 まず冒頭3小節間から問題が起きますね。とにかく慣れてください。そしてある程度慣れてきたら、1小節目1拍目のCisのオクターブを弾く際に、左手5の指をよく鳴らし、伸びのよい、深みのある低音を弾いてください。このCisの余韻が3小節間残るくらいに大切に扱います。さて、この曲の1つの特徴として、ショパンが持ち前のポリフォニーの腕前を十分に発揮している曲とも言えます。層は厚く、多声部に書かれている場所も多くあります。冒頭3小節も、メロディーラインとそうで ないラインを区別して、混同させないようにします。例えば1小節目、筆者がよく耳にするのは、gis eis cis fis gis と聴き取れます。しかし実際は、gis fis gis の3つの音のみです。内声を控えて下さい。また、ルバートを十分にかけて自由なカデンツとして弾いてください。 この曲の「癖」としては2拍目にストレスが来ることにあります。1小節目も2拍目が最もテンションの高いところですね。同じく6小節目から始まるメロディーラインも2拍目からスタートします。そして1拍目は「前のフレーズの終わり」を意味します。故に1拍目にアクセントは禁物です。例えば、8小節目。1拍目は7小節目の最後の音になりますので消えるように弾きます。そして2拍目から新たなフレーズが始まります。以下、このようなパターンは全て同じようにお考えください。 主題に関しての助言です。6-8小節を例に取ります。6小節目2拍目から始まるフレーズは8小節目の1拍目で終わりになります。ラインをよく見ると、Cisから始まり7小節目で一番高い音であるFisに達し、そこから下行して行き、8小節目でpになりますね。ここからは個人の考え方に委ねられますが、筆者であれば7小節目のFisにはそれほど音量を与えません。むしろ次のAis Dis Cis Fis H をクレシェンドして、このフレーズの最も大きい部分とし、最後のAisはDiminuendoで達したら、そからさらにdiminuendoで内声を下行させ、最後の8小節目の和音にたどり着きます。 もう1つだけ例を取ります。次のフレーズは8小節目の2拍目から始まり、10小節目の1拍目で終わります。同じく9小節目の最も高い音であるHには柔らかく達し、その後2拍目にあるGisisなどの非和声音が実に色っぽい、感情的な、悩ましい和音を演出しますので、そこはテンションを上げます。そして先ほどのフレーズと同じようにDiminuendoで4拍目のAisに達し、10小節目の1拍目はそこまで大きくしません。 これらのフレージングはあくまで筆者の考え方ですので、そのように弾かなければならないという事ではありません。参考にして頂ければと思います。 11小節目、4拍目で突然カラーが変わります。急激な音色の変化をつけます。11-12小節間の左手も弾きにくいですよね。分散和音の真ん中の音であるCisを左手の3の指でとり、練習の際も演奏の際もこの3の指をCisから離さないようにすれば、より確実なロケーションの確保が可能になります。つまりは3の指を頼りに、他の音の位置を覚えてしまいます。 14小節目から登場する16分音符の6つの6度は後に曲中に多く出てきます。この曲の1つの特徴でもある素材です。しかしながらこれがなかなか弾きにくいですね。筆者であればペアで練習します。例えば、15小節目、2拍目の最初のペアは Fis Dis と Dis His です。まずこの2つだけを練習します。弾けるようになったら次の2つ、これも弾けるようになったら次の2つ、というように、練習をしていくと良いです。6つの16分音符をまとめて練習してもなかなか上手くいかない場合はこのようにされると良いでしょう。 もう1つ助けになることとしては、この6度のユニットがオクターブになる箇所がありますね。例えば、14小節目の最後の右手の音です。6度からいきなりオクターブというのは辛いですね。そこで、このパターンにオクターブが出てきたら、そのオクターブの下の音は左手でとります。そうするとかなり弾きやすくなります。 34小節目のように、同じ和音、同じパターンが何回も続く箇所もこの曲にしばしば見られますね。これは、湖などの波で船が繰り返し揺れている様子でしょうか。いずれにせよ、機械のように同じに弾かずに変化をつけてください。この34小節目の2拍目からはrallが書いてあります。ですのでその通りにするのですが、その時ちょっとしたコツがあります。2-4拍目の両手にある装飾音のタイミングを音楽が進むにつれて少しずつ実音との間隔を空けます。すると衰退していく感じが出ます。 42小節目の1拍目に出てくる右手の16分音符上行形は、またもう1つの素材です。これはレゾネンスの役割を果たしている音形ですので、決して強くせず、ソフトペダルを踏むなりして、別世界の音質を作って下さい。以降、このパターンは全てその処理で演奏します。 兎にも角にも最後の3ページは本当に大変です。いつか弾けるようになると強く信じて根気よく練習して下さい。左手は特に重要ですのでがっちりと和音に指がフィットするように、ゆっくりと丁寧に練習して下さい。 107小節目1拍目をご覧下さい。1つの盛り上がりがゴールに達する部分です。こういう場所はフォルテで強く表現したいところなのですが、右手のアルペジオはオクターブ以上離れている弾きにくい和音で、最後に担当する5の指も黒鍵ですね。白鍵であればまだしも、黒鍵は太さが細いので、ミスタッチをしやすくなります。ここはミスタッチを避けたい場所です。そのようなとき、最高音のGisを5の指で取らずに、1の指で取ると安全で、しかも大きな音を出すことができます。下から、1、2、3 と取り、5に行かず、再び1でgisを弾きます。お試し下さい。
ピティナ&提携チャンネル動画(14件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(8件)
楽譜
楽譜一覧 (8)

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Peters