
解説:野原 泰子 (626文字)
更新日:2007年6月1日
解説:野原 泰子 (626文字)
ロシアの作曲家。ロシア国民音楽の創始者として知られる。スモレンスク近郊ノヴォスパススコエ村の地主の家に生まれ、教会の鐘の音と農民の歌に囲まれた環境で育った。15年から音楽を学び、18年にはジョン・フィールドのレッスンも受けている。ペテルブルグの貴族寄宿学校を卒業後、運輸省に勤務(24~28年)。職務の傍ら、ロマンスやピアノ曲、室内楽曲を作曲して社交界の注目を浴びる。
30~33年にはイタリアで音楽を学ぶ。ベッリーニやドニゼッティのオペラを始め、同地の最新の音楽から大いに刺激を受けながらも、ロシア人としてのアイデンティティを強く自覚。帰国の途上のベルリンでは、音楽理論家ジークフリート・デーンから教授を受けて、自らの方向性に確信を抱く。
帰国後、オペラ《イヴァン・スサーニン》(36年)を作曲。イタリア歌劇の形式によりながらも、ロシア民謡を素材とする国民的題材のオペラは、古い民話に基づく《ルスラーンとリュドミーラ》(42年)と共に、ロシア国民主義のオペラの礎石となった。
1844年のパリでは、ベルリオーズの色彩的な管弦楽曲に魅了される。その翌年に管弦楽の素材を求めてスペインへ発ち、同地の情緒溢れる旋律で2つの《スペイン序曲》を作曲。これに自信を得て、帰国後《カマリンスカヤ》(48年)に着手。イタリア風の音楽が主流だった当時のロシアの楽壇において、ロシア民謡による管弦楽曲を書き上げたことで、管弦楽の分野でも国民楽派の祖としての貴重な足跡を残した。
作品(57)
ピアノ独奏曲
曲集・小品集 (4)
変奏曲 (7)
マズルカ (7)
ポルカ (2)
ワルツ (5)
リダクション/アレンジメント (5)
種々の作品 (7)
ピアノ合奏曲


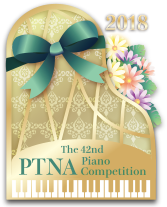 コンペ課題曲:A1
コンペ課題曲:A1
 ステップレベル:応用1,応用2
ステップレベル:応用1,応用2